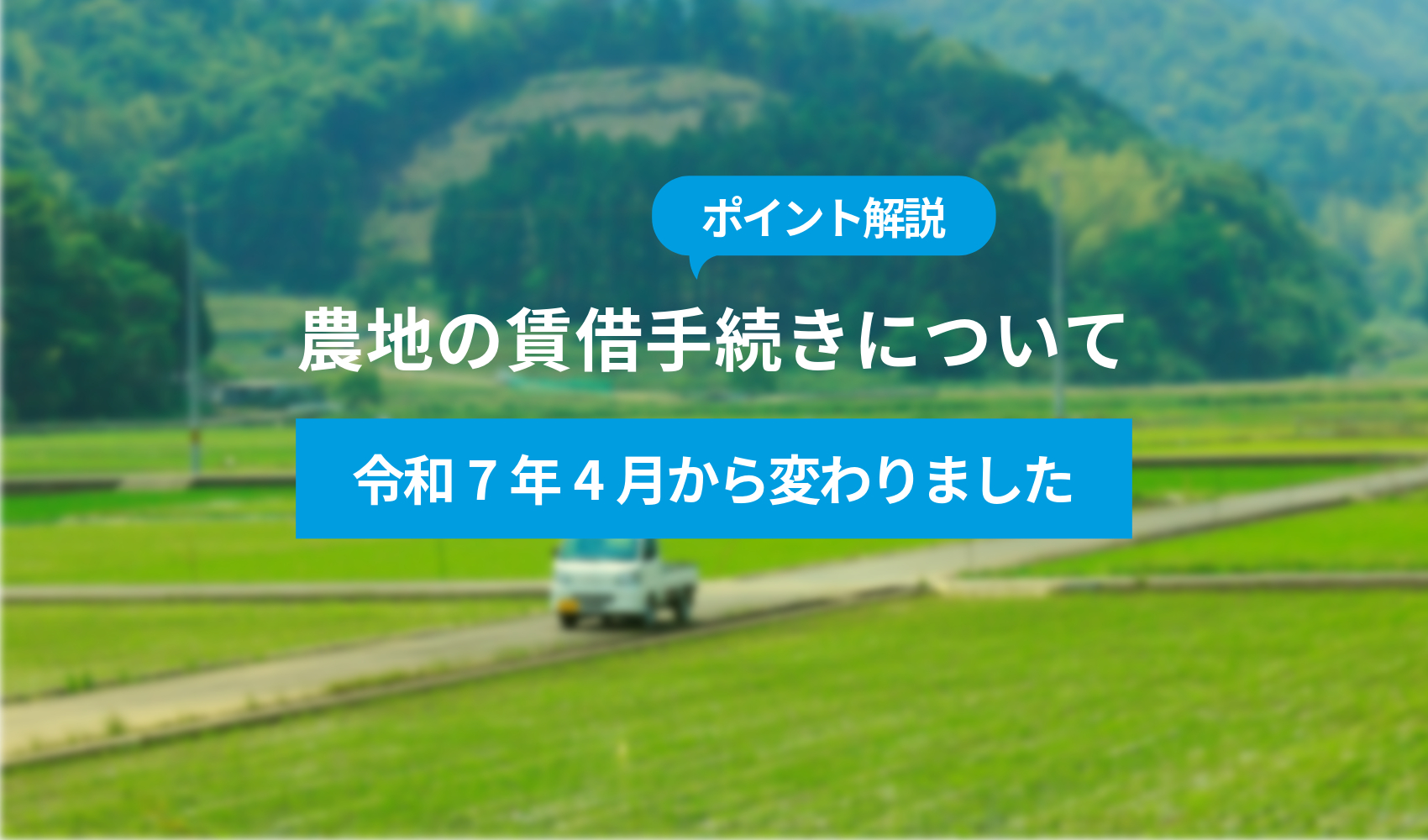 NEW
NEW
農地の賃借手続きについて
農業経営基盤強化促進法の改正に伴って、「利用権設定事業(相対での農地貸借)」が廃止されることから、令和7年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は「農地中間管理事業を介した農地貸借」に移行しました。
こちらのコラムでは農地中間管理機構について、また農地を借りるにこれまでとの変更点やよくある疑問を解説します。
農地中間管理事業とは?
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
農地中間管理機構は、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等へ貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。
農地法第3条による貸借も可能?
農地法第3条を用いた賃借も引き続き可能です。ただし、原則は農地中間管理事業経由の貸借とされます。
なぜ農地中間管理事業に一本化するのか?
- 遊休農地の有効活用 - 農地の流動性を高め、貸し手・借り手のマッチングを促進
- 不適切な農地利用の防止 - 転売や投機目的での利用を防ぎ、農業の適正な継続を支援
- 農業政策との整合性 - 自治体の「地域計画」に沿った貸借が行われる
農地中間管理事業を介して農地を借り受ける場合、どのような手続きが必要となりますか。
1 農業委員会が出し手・受け手の意向を確認し、地域の農業者等の関係者の話合いを踏まえて市町村が地域計画を作成します。この地域計画に基づき、農地バンクが市町村や農業委員会等とも連携して、出し手・受け手が希望する貸借の期間、借賃、借賃の支払方法等について調整を行うこととなります。
2 こうした調整の後、農地バンクは促進計画を作成し、都道府県知事の認可・公告を経て、受け手は農地を借り受けることとなります。
3 農地バンクが促進計画を作成するに当たって、受け手が用意する書類
- 現に使用収益等している農地の利用の状況
- 耕作に必要な機械の所有の状況
- 農作業に従事する者の数及び配置の状況
- 法律その他の農業に関する法令の遵守の状況
- 受け手が個人の場合、耕作の事業に必要な農作業への従事状況
これらの一部を省略できる場合もありますので、詳細は農地中間管理事業または、農地を管理する自治体にお問い合わせください。
認定農業者である必要はある?
農地中間管理事業を利用する場合、必ずしも認定農業者である必要はありません。ただし、認定農業者であると、補助金の利用や審査がスムーズになるなどのメリットがあります。
新規就農者でも借りられる?
新規就農者も農地中間管理事業を利用できます。ただし、事業計画の提出が求められることがあり、自治体の支援を活用するのが望ましいです。
農地にハウス等の農業用施設を設置したい場合は?
農地バンクから借り受けた農地に農業用ハウス等の農業用施設を設置しようとする場合は、農地バンクの同意が必要であり、農地バンクは出し手の承諾を得た上で同意することとなります。また、契約が終了した場合には、自分が設置した農業用施設を収去して原状を回復する義務を負うことになるのが一般的な取扱いです。
なお、農業用施設の設置については、一般的に農地転用の許可が必要となりますので、農地の所在する農業委員会にご相談ください
ハウスの施工会社を選ぶ際には複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することが大切です。
メガデルに無料会員登録をすると、実際に施工会社様と繋がることが可能です。
是非、会員の登録をお願いします。
